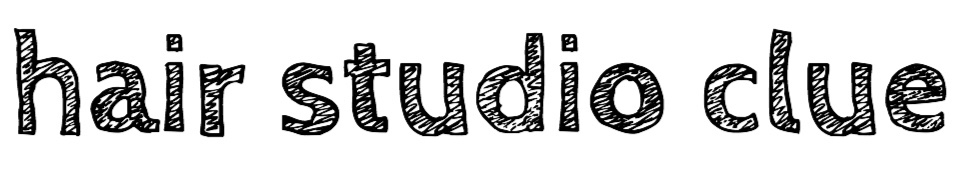【3月11日の海。―支え―】
(先に「―襲来―」をお読みください)
「こ、こんなのどうすんだ……」
家の中の片付けは、とりあえず持ち上がりそうなところから取りかかりました。一つ一つ丁寧に運び出すというよりは、「あれもだめだ、これも使えない」と、半分やけのような気持ちがありました。はじめの頃は、何もかも家の前に放り出す、といった感じだったかもしれません。
波に押されて来た姪の車、月極めの車庫に大切に保管してあった兄の車もそれぞれ確認しに行きました。一度海水に浸かってしまうとだめだと聞き、二台とも廃車となりました。
しばらくすると、また手伝いをしてくれる親戚が増えます。皆、必要な会話ぐらいはするようになり、要るもの要らないもの、使えそうなもの、と、ある程度落ち着いて作業が出来るようになってきました。誰がリーダーでもなく、皆が自分自身で役割を選び、黙々と作業に没頭しています。
居間、店、裏庭、車庫、と散乱の様子は様々でしたが、海の黒い泥は所構わず、見事に行きわたっていました。

私はまず、店を中心に片付けました。備品など細かい物も多く、使えるか使えないかの判断も、ある程度わかります。二階を支えている隅柱が完全に折れているため、修復を急いだ方が良いと思い、柱周辺を早めに片付けておきました。余震が起こるたび、崩れてしまわないかと、心配しながらの作業が続きます。



「翌日」は瞬く間に終わり、しばらくは私の家が避難所となります。水道は止まっていましたが、電気は大丈夫です。車も七、八台停められ、休憩したり、片付けの下準備をしたりするのに適所となっていました。風呂は次兄の家で利用させてもらい、気力体力共に疲れた私たちは、「明日もやらねば」という思いを抱き、早く眠りにつきました。
悲報と二次災害の恐怖
13日の朝、早々に支度を始め、前日よりも色々と準備を整えて片付けに向かいました。私は花粉アレルギーのためティッシュも箱ごと持参。実家との行き来をしている自転車も小型で担ぎやすく、とても活躍してくれました。
早速作業に取りかかるのですが、次々と運び出される様々な家財道具により、家の前はあっという間に山ができました。道路を挟んだ駐車場兼物置の方も片付けが進んでいます。門柱に乗り上げていた四駆車も、近所の友達のおかげで早めに動かすことができました。また、山の方から引いてある水が使えるため、泥が付いていたものをキレイに洗い流すこともできます。
余震が頻発する中、順調とは言えませんが作業は黙々と続きました。
その日の午前中だったと思います、突然、八百屋の奥さんの悲報を聞きました。旦那さんも一緒だそうです。奥さんはとても穏やかで、旦那さんはいつも元気で優しそうな方。二人で一生懸命お店を切り盛りしている姿が印象的でした。小さいころから馴染みのあるお二人。奥さんはここ何年も髪を切らせていただいていました。
私の中では「逃げられたはずだ」という思い込みがあり、何かの間違いだという考えが頭の中を巡りました。それからしばらく色んなことが頭を交錯し、作業する腕には力が入りませんでした。ただただ・・残念でなりません。
店の方はやがてスペースができるようになり、厄介な泥も掻き出しやすくなってきます。しかしこの泥が大変でした。戸袋や排水パイプ、内壁に至るまで入り込み、充分に掻き出すことができず、「あくせく」とした作業が続きます。
気分も乗らず、根が詰まりそうになった私は、駐車場にいる甥の方へ行きました。いい空気でも吸いたいのですが、風も強く、ホコリと花粉で鼻と目はグズグズ。
倒壊したブロック塀を片付けていると、近くからザワザワした音が聞こえてきました。
今度は「火災」です。二軒となりの家の裏にある平屋から火の手があがり、ものすごい煙が立ち昇っています。実家から直線で20メートルのところです。

消防庫が隣にあるのに、当然出動できません。しばらくして消防車が近くに到着しますが、状況が悪くなかなか放水もできません。こちらにも燃え移ってしまうことを考えると、恐怖がこみ上げてきました。
津波を背に自転車をこいできた時よりも、恐怖でした。
「みんなで一生懸命協力してる事が無駄になる!?」
そんな風にも考えながら、一旦私の家まで離れ、一刻もはやく鎮火してくれることを祈りました。パンパンになったホースは連結され、数百メートルも離れた防火水槽まで届いています。
しばらくして煙は徐々に小さくなり、鎮火したことを聞きました。全焼したものの、逃げ遅れた人もなく、何とか延焼もせずに済んだようです。その後、気を取り直して作業に戻ります。
混乱の中で見えたつながり
津波後、私の心配している事の一つに波崎方面の被害状況がありました。知り合いやお客さんも多いところです。私が津波到達時に海を見ていた際、波はかなり東方向から向かってきています。震源に対して正面に位置する場所なので、飯岡地区よりも被害は大きくなっているだろうと考えていました。
震災から一日以上経過しているのですが、何だかこちらからは連絡することが出来ませんでした。
そして二日近く経った頃でしょうか。携帯が鳴ります。長年通ってくださっている波崎のお客さんSさんからです。まず、その方が電話をかけられる状態にあることにホッとしました。
旭市というか「飯岡」の津波被害が大きいという事を知り、心配で連絡をくれたようです。私からも「そちらはどうですか?」と聞くと、波崎は津波による被害は大きくはなく、水道が止まり、一部液状化がひどいという事を聞きました。他にも心配をいただく電話はありましたが、最初の連絡ということもあり、すごく嬉しかったのを覚えています。
余震にも慣れ、それぞれ落ち着いて作業を進めている中、またも騒ぎを感じました。今度は津波警報が発令され、「避難して下さい」という防災無線です。

火災避難から、さほど時間は経過していません。警察官も笛を鳴らしながら誘導します。当然皆さんも「津波」という言葉を聞いて、慌てて高台に向かいます。
私は(なぜ今津波警報が鳴る?)と思い、不思議でなりませんでした。
妻には後からすぐに行くと伝え、子供たちをまかせます。他の家族も全員車で避難しました。自分の家も充分な戸締りをせず、空けたくもなかったので、車のエンジンをかけ、駐車場で待機することにしました。
海側の交差点には消防員が残っていて、その場所から海を警戒してくれています。大きな揺れも無いのに何で警報が出るのか腑に落ちませんでした。向かいの家の旦那さんも外に出て様子を伺っています。
釣り仲間が言うには「海は至って静かだし、引いてもないし、津波来ないよ」とのこと。そのまましばらく駐車場で様子を見る事にしました。
二十数分くらいでしょうか、「津波警報は誤報でした」というお知らせ。
この時はまだ多くの人が「過敏」、であるのは仕方ありません、やれやれでした。
花粉と砂ホコリで鼻水が垂れるのもお構いなしに作業続行。長く感じましたが、その日もあっという間に日が暮れてきました。
支えと希望
家で子供たちの面倒や、留守番、情報収集、みんなの食事の支度などを整えてくれる妻、そして姉らのおかげもあり、一日中片付けに集中することが出来ています。
また、福島原発の水素爆発後に小雨が降った事があり、それについてすぐに危険性を教えてくれたのも妻でした。片付けの現場にいると、それどころじゃないと思うかも知れません。しかし、後になって考えれば重大な事を指摘してくれていました。「冷静に考える」いつも自分が言っていることでした。
翌朝も目が覚めると、すぐに確かめる事があります。
地震と津波は夢じゃなかった。筋肉痛もある。一階には兄たちも寝ています。
現実です。
今日も一日でどれくらい片付けられるか、ガレキの回収は来てくれるのか、様々な事を考えながら支度をしました。
”現場”に着くと、まず前日引き上げた時と変化がないかチェックします。わかりづらい状態でしたが、人が忍び込んだ形跡が無いか一通り見て回りました。
小網町通りは、各家から出る廃棄処分となった家財道具が山のように積まれ、車両がなかなか通れません。それでも他より早い段階で回収車がまわって来てくれました。最初に来てくれたのは地元の建設業者のダンプカーです。その中から降りた一人は飯岡の同級生で、久しぶりだったのですが、昔話をするわけでもなく、大きい体でガレキを次々と積み込んでいってくれました。
そして、私の幼馴染みの実家もすぐ近くにあり、やはり一階は全滅。お姉さんの旦那さんも手伝いに来てくれているようで、電気の復旧作業をしていました。ひと段落ついたらウチの方も見てもらえるようお願いしたところ、すぐに来てくれて、玄関に一カ所だけ、臨時のコンセントをつけてくれました。
「すごい!なんていい人だ……」
これで電気工具使えたり、電化製品の確認もできたりするぞ。見てもらうだけのつもりだったので、思わず感動しました。
やがて一階のものが大体運び出されると、やはり泥の掻き出しが主になってきます。初めのうちは大きい角形スコップで中の泥を何度も何度も外に運び出しました。
途中から私は裏庭と排水溝の方にまわりました。区別がむずかしく、作業のしづらい場所です。裏庭では、元の土を削らないよう海の泥だけをすくい、狭い通路を通って表に出さなければいけません。土の色が多少違うものの、馴染みの無い人には、とてもむずかしい作業です。小学校の頃、裏庭の隅っこで隠れて遊んでいた記憶をたよりに、一人奮闘しました。
排水溝の泥もしぶとく、甥と二人、小さなスコップを使い、かがみながらの作業が続く中、腰痛を再発させるハメとなってしまいました。
店、居間、台所、和室、全て水を流せるようになるまで四日ほどかかったと思います。

その間、兄はぶ厚いドブ板で指を挟み、母と叔母は同じ場所で同じようにデコをぶつけ、皆、疲労を溜めながらの慣れない作業にてんてこまい。次兄は市役所務めの為、連日泊まりがけで「東奔西走」の忙しさでした。
精神的ショックもありましたが、叔父さん叔母さんはじめ、いとこらの助け、温かいカレーやおにぎり、レトルトやドリンクの差し入れ。心配で、家まで訪問してくれる人もあり、笑顔も自然に戻ってくるようになりました。
中にはビックリするような偶然もあったのです。
津波から四日目の頃、妻にみんなの夕飯どうしようかと聞かれました。私は「そろそろ惣菜でも食いたいなぁ」と言いました。「鳥忠(とりちゅう)」行ってみる?となりの銚子市で人気の惣菜屋さんです。「時間かかるしどうしよう」「でも食べたいよなぁ」と、何となくその場は話だけになってしまい、結局少し残っているものをおかずにしよう、という事になりました。
そしてその夕方、家に引き上げてしばらくすると「ピンポーン」とインターホンが鳴ります。
「銚子の〇〇〇〇です」
私の元に15年近く来てくれているお客さん、Tさんです。やはり”飯岡”という事を聞いて心配になって来てくれたそうです。手に持つ包みからは何やらいい香りが……。「こんな物の方が良いと思って」と、差し出してくれました。
なんと、さっき話していた「鳥忠」の惣菜ではありませんか!
ビックリした私はついお礼をしつこくしてしまいました。引き寄せ? いやいや、相手の思いやる気持ちの結果です。大量に頂戴した惣菜はみんなでおいしくいただくことが出来ました。
復興への誓いと義務
五日目、家の前に出された「ヤマ」もだいぶ回収され、中の片付けもひと段落。駐車場も整理され、あとは消毒を行い、修復も早く済ませたいところです。全部のコンセントも電気屋を待つばかりとなりました。
その頃になると、広めの道路は自転車ならスイスイ通れるようになっており、隣の町内や海寄りの方へ走り出てみる事にしました。

何も手つかずの場所、一人で片付けをされている方。狭い路地ではまだ一度もガレキを回収できていない所もあり、一軒一軒目にするごとに気持ちが沈み、戻る時には自転車を降りて歩いて帰って来ました。

やがて、消毒と隅柱の修復がとりあえず終わり、店、廊下を含む一階すべての床の張り替え、壁、建具、ひとつづつ進み、各部屋に灯りが戻ったのは六日目からだったと思います。

そして、鍵も全部かけられるようになり、台所にも新しいフローリングが張られ、暖もとれるようにまでなりました。一方、私の家の方も水道が戻っていたので、一階のトイレ、風呂、仕事である店のお湯も出せます。あとはゴミや砂、荷物等を片付け、キレイに掃除をすれば仕事を再開できます。
予約の電話も心配して下さる声と共にいただけるようになりました。
私の店は翌日の18日より再開。約一週間の休業です。
再開してすぐの日は、お客さんの合間に残りの片付けをしに行きました。ボランティアの方々が見え始めましたのはこの頃です。人手が足りず、片付け等が滞っていたお宅は助かったと思います。
実家では、店がごちゃごちゃになり、やる気が失せてしまっていた母も、初めの頃の様子とは違います。使えるものを集め、キレイに洗った椅子も並べ、ハサミやクシ、その他備品などを整えはじめていました。
ショーケースやシャンプー台、促進器などの機材も新品とはいきませんが、インターネットで母の使いやすそうなものをさがし、手配しました。道具が揃うにつれて、母の気持ちも再開に向かっていったと思います。
津波で壊れてしまった物や、廃棄処分となってしまった思い出詰まった家財道具たち。いたるところに傷も残っていますが、家族全員無事だったことが何よりも幸運に思いました。
「大規模半壊」という結果になりましたが、沢山の方々の協力により、私の実家は、被害の割には早く復旧が出来たと思います。
その後も、力士やプロ野球選手、歌手、天皇陛下と皇后さままでも慰問に来てくださいました。



長男の入学式も遅れはしましたが、TVでも採り上げられ、温かい拍手の中執り行って頂きました。

そしてまた、津波に襲われたにもかかわらず、同じ場所に家を建てる勇気のある方。再起が危ぶまれた山中食品さんも立派に立ち直り、国民宿舎飯岡荘(現:いいおか潮騒ホテル)も再開の目途がたっています。
四年が経過する今では、復興住宅、避難タワーも完成し、堤防もかさ上げ工事も順調に進んでいます。
しかしながら、倒壊してしまった家屋も多数、〈死者13名、行方不明者2名〉といった悲しい事実があることも忘れてはいけません。
今も同じ飯岡の人に話を伺うと、自分の体験した事や、見た事、感じた事や伝えたい思いが、溢れるように言葉が出てきます。一人一人にストーリーがあります。
私も、一人で海に向かったことに対し、妻から叱責を受けました。有り難いことであり、反省しなければなりません。
震災前に体調を崩し、2012年に他界した父も、飯岡の津波被害について、晩年を費やし、「短歌集」や「手ぬぐい」として記録を残していきました。

「忘れる」ということも、前向きに生きるため、人間にとって必要かもしれません。

ですが、この日、3月11日に起きた「津波」は数多くのことも私たちに教えていきました。自ら体験し、目にした人たちは、そのことも踏まえ、多くの記憶と共に、多くの”記録”をきちんと残しておく義務がある、とわたしは思います。
最後に、
今だに私の心に強く残っているものは、津波が引いてゆく際の妙な静けさ。きっと、その中にはまだ見つからない大切な教訓が、あるような気がします。